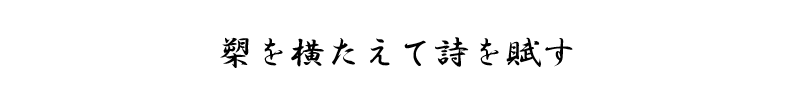人は二度死ぬということ
人は死んだとき、実は半分しか死んでいない。人は、自分の死後に誰からも思い出されなくなったときに本当に死ぬのである。
これはとても金言ではあるが、誰が最初に言ったのかは定かではない。ネイティブアメリカンの諺だという人もある。有名な漫画であるワンピースのDr.ヒルルクも同様のことを言っていたのを思い出した。
一度目の死は、呼吸が止まり、心臓が動かなくなったときだ。この肉体を通しての私の活動が終わりを告げて、もう二度と、人と触れ合うことができなくなる。とても辛いことだ。しかし、私のことを覚えてくれている人が生きている限り、私はその誰かの心の中で生き続けることができる。その人の心の中で、私は会話をすることだってできる。一度目の死への恐怖を紛らわしてくれる優しい言葉だ。
しかし、二度目の死によって、私は、もうこの世の誰からも思い出されることがなくなる。まるで、私という存在がなかったかのようだ。私の死後に、たまたま私の名前をどこかで誰かが見かけたとしても、それはただの記号にすぎない。私という存在が色を持って伝わらなければ、誰かの心の中で私と会話できるようなレベルでなければ、それは誰かの心の中で生きているとは言えない。
二度目の死さえ、確実に訪れる
私の死後、誰からも思い出してもらえなくなったとき、私は二度目の死を迎える。もちろん、誰からも忘れられてしまうということが、現実に生きている私にとって身体的な痛みが伴うわけではない。本来は、それを辛いと思うことが理にかなっていない。しかし、心にはチクりとしたものを感じてしまう。それが人間だろう。そうか、人は、忘れられたくないのだ。自分が無かったことになるような気がして、自分の存在が完全に否定されたような気がして、辛いのだ。
現実の世界で地位や名誉を得た人が、こぞって自分の名前を後世に残そうと考えるのは、こういうことが要因なのかもしれない。歴史に自分の名を刻むことで、自分の死後、多くの人々に思い出してもらえる。そうすれば、自分の二度目の死というものを幾ばくか延ばすことができる。つまり、人は、本能的に二度目の死を理解しているのかもしれない。
ほとんどの人たちは、自分が死んで百年も経てば、誰からも思い出されることはなくなる。普通の人にとって、自分のことを思い出してくれるのは、自分の子や孫までである。もしも運良く、歴史に少しでも名を残すことができても、よほどの偉人でもなければ、もう百年が限界である。そして、どんなに偉人でも数千年の時を超えることはほぼ不可能である。私たちが今から二千年前の人々をどこまで覚えていようか。キリストやアリストテレスや始皇帝のようになることなど不可能と言ってよい。さらに、この先の数万年ということにもなれば、人類が生き残っているかもわからない。
今に、生きよ
歴史に名を残しても、二度目の死は確実に訪れるのだ。もしそうなら、歴史に名を残そうとすることなど、徒労ではないだろうか。歴史に名を残すために、一度目の死を迎えるまでに得られたはずの喜びを蔑ろにしているとしたら、なんて無意味なことだろうと思う。
昔、このような記事を読んだ。人の死を看取ってきた看護師の話だが、死に直面している患者が最期に最も口にする人生の後悔は「もっと自分のために時間を使えばよかった」ということだそうだ。私たちは普段、自分に残された貴重な時間を意識することはなく、直面して初めて、自分にそれほど時間が残されていないことを自覚するのだ。
世間体を気にして自分のやりたいことを主体的に選択してこなかった自分、周囲の人の期待に応えるために時間を使ってしまった自分。人の期待に応えるということは、自分の期待に応えることとは違う。
現実に生きている私たちにとって、生きているうちに幸福であろうとすることの方が重要だ。生きている間であれば、いくらでも楽しい思いをすることができる。生きているうちに楽しまず、死後のことを心配するなんてどれだけ馬鹿なんだろう。どんなに歴史に名を残しても、結局の運命は変わらない。いずれ私たちは、人類の血統によって脈々と続く永劫の流れの中の一部となるだけである。