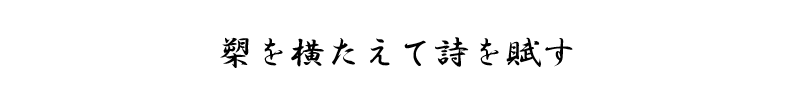「茶の本」は、日本の文化を西洋に初めて知らしめた本
今日は、日本における美術の神様、岡倉天心が書いた『the Book of Tea(茶の本)』を紹介したい。岡倉天心とは日本の近代美術に大きな影響を与えた偉人である。東京藝術大学の前身である東京美術学校の創設や、今日紹介する「茶の本」によって日本の哲学を欧米に広めたことでも知られている。
岡倉天心が生きた明治は、文明開化によって西洋文化が急激に日本へ入り込んできた時代である。当時、西洋では、技術の遅れている日本は文明後進国と見られており、当の日本人も自分たちの文明より西洋のほうが優れていると考えていた。日本国中が西洋に憧れていた時代だったのである。福沢諭吉の学問のすゝめなど、当時の博識の文化人が書いた書籍を読んでも、西洋の技術や文化がいかに優れているか、日本はそれにどうやって追いつかなければならないか、といったことが多く説かれている。
しかし岡倉天心は、自分たちの文化や美術に目を向けて、日本の伝統文化や美術の優れた価値を西洋に広めようとした。彼は日本の伝統的な侘び寂びという哲学に目を向けて、それを「茶の本」として英語でまとめ、西洋でベントセラーにまでなったのである。この「茶の本」によって、日本の侘び寂びという哲学が西洋で認知されるようになったことは、日本の文化にとって大きなことであった。
侘び寂び、わび茶は、簡素や古びたものを愛する文化

岡倉天心が日本の文化を発信するにあたって「茶」を取り上げたのには理由があると私は思っている。そもそも西洋における茶は、1609年にオランダへ日本の茶が輸出されたことで初めて伝わったものである。西洋で初めて飲まれたお茶は、中国の茶ではなく、日本の緑茶だったのだ。その後、中国貿易を独占していたイギリス東インド会社によって、中国産の紅茶が西洋におけるメインストリームになった。紅茶は今や西洋の文化というイメージが強いが、日本や中国から西洋に茶が伝わるまでは、西洋に喫茶の習慣はなかったのである。そして、アフターヌーン・ティーの習慣が始まり、西洋で根強い人気を獲得しはじめた「茶」を通じて、日本の侘び寂びという文化を伝えたのがこの本なのだが、「茶」を題材にすることは注目を集める意味でも重要だったのではないかと想像する。
茶の歴史についてもう少し触れると、日本における茶は、奈良時代に中国から伝来したのが始まりだ。その後、喫茶の習慣は一度廃れるが、宋で禅を学んだ栄西禅師によって再び日本へ持ち込まれた。一方の中国では、北方から元(チンギス・ハーン)に襲来されたことで、南宋に根付いていた茶の文化が絶たれてしまう。その後、日本では室町から戦国時代へと移り、千利休がわび茶として日本独自の様式美を完成させることになる。
茶を飲むという文化は、栄西禅師から伝えられたということから分かるとおり、禅(さらには道教)の流れを汲んでいる。そこには、故意に何かを作り込むのではなく、自然のまま、不完全なままを愛するという精神が根付いているのだ。ここが西洋の文化とは決定的に違う。西洋の文化では、色々な装飾を施して豪華絢爛であることを尊いものと考える。西洋の建築物や絵画を鑑賞すると、その複雑な構造であったり、入念に装飾が施された美しさを感じるものだ。一方で、侘び寂び、わび茶といった日本の文化は、簡素や古びたものの中に美しさを見出すものである。
西洋は日本の文化から学ぶべき
西洋は何かを付け足していく足し算の価値観、日本は余計なものを削っていく引き算の価値観だ。これはなかなか西洋人には理解しづらいことだろう。簡素なものは、西洋人にとっては貧相なものに映るのではないか。しかし、日本人にとっておびただしい数の装飾品で飾られた西洋の美意識は、いたずらに富を誇示した感じさえ与える。
岡倉天心はこの本で「西洋は東洋から学ぼうとしない。たとえば、キリスト教の宣教師を送り込んでキリスト教を伝えようとはするものの、送り込んだ先の現地から何かを学ぼうとはしていない」と言い放つ。本来であれば、豪華絢爛を良しとする西洋の美と、簡素で最小主義的な日本の侘び寂びは、全く異なるものである。物質主義が蔓延している西洋においては、茶の湯に代表されるような簡素の中に美を見いだす日本の美は、非常に参考になるはずではないだろうか。
最後に、わび茶の世界を少しだけ伝えておきたい。わび茶は、一般の世界から隔離された小さな茶室で営まれる。外界と茶室を隔てるのは、露地と呼ばれる細い通路だ。露地を抜けると、茶道口という茶室への入り口がある。ここがとても狭く、屈まないと中に入れないように高さが設定されている。これには、どんなに身分が高くても腰と頭を屈めて入る必要がある、なぜなら、茶室の中では将軍であろうと庶民であろうと人は皆平等だからである、という意味が込められている。そしてようやく茶室の中に入ると、主人が客人をもてなすために一杯の茶を淹れる。掛け軸と一輪の花のみが存在する簡素で小さい空間の中で、主人と客人が一人の人間として向き合う。真のもてなしというのは、こうした逃げ場のない空間で、心と心が真正面から相対することなのだろう。