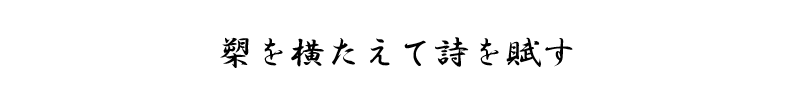精神と身体の融合
字を書くこと。それは、スマートフォンの画面を親指で擦って文字を打つような現代的な行為のことではない。人が生まれたときから持っている最高の道具である「指」を使い、ペンが紙に擦れる絶妙な音に耳を傾けながら、十人十色の筆跡によって文字を紙の上に書き出す行動を指す。
最近は、ビジネスの現場でも、ノートや手帳を持ち歩く人はほとんどいなくなった。何かを書き留めておきたいときは、スマートフォンの中のメモアプリやスケジュールアプリに書き込むだけで済んでしまう。現代では、記録するという目的において、字を書くという手段は合理的ではないということだ。ノートや手帳やペンを物理的に持ち歩くことは、大変な手間だということだろう。
しかし、本来、ノートに字を物理的に書くという行為は、情報を記録するという表面上の価値だけに留まらなかったはずだ。指や腕を使って字を書くことは、スマートフォンの画面を親指で擦るよりも、遥かに脳を刺激していたからである。
仏教の修行には、写経というものがある。お経を書き写すことによって、功徳が得られるという修行であるが、最近では、写経をすることで精神の安定にも効果があることが認められている。この効果は、写経に限ったものではないようで、字を紙などに書くという行動自体に精神安定の効果があるそうだ。
字を書くといういわば肉体の活動を通じて、心と身体が一体化する。写経では、筆を持つ指や腕、染み渡る墨汁を見つめる瞳、そして半紙が擦れる微かな音を捉える耳までもが、正しく字を書こうとする精神と繋がっていく。これと同じような体感が、ボールペンで紙に字を書く場合でも得られる。字を書いている間は、その空間が外部から切り離され、小川に足を浸しながら、静かにせせらぎに耳を傾けているかのように、ゆったりとした時間の中にいる気持ちになれる。
目的を持たず、ただ行動に集中する
字を書くことそのものは、目的を持たない行動である。人は普段、何かを記録するといった目的をもって字を書こうとすることが大半だと思うが、字を書く行為そのものは、単なる動作に過ぎない。
字を書くときには、様々な目的が出発点となる場合がほとんどである。たとえば、情報の整理、情報の記録などがそれである。しかし、どれも目的を先に立たせてしまうと、精神の安定という貴重な効果は得られない。目的を持たずに、ただ字を書くという行動をしたときのみ、字を書くことそのものに集中することができるからである。そして、現在とは別な空間を作り出すことができ、その結果、精神の安定が得られるのである。
これは、曹洞宗の只管打坐の考えに通じる。目的を持たずにただそこに坐る、それによって悟りを得るというのが只管打坐である。悟りを得るために只管打坐をするのではない。そういう目的を持った修行では、悟りには近づけない。ただ、そこに坐る。そして今を見つめる。悟りをひらくということは結果論に過ぎないという考え方である。
目的は副次的なものとして、行動を中心に考えることは、いかにも人間らしいといえるのではないか。人は行動の生き物である。思考してばかりでは、身体に毒なのだ。これは、何万年も前から生きてきた私たちの身体そのものの仕組みであるから、覆すことはできないのだ。
ただ漫然と字を書き続ける
写経のような敷居のある行動ではなく、いますぐに、普通に字を書きたい、そのような人には、目的を持たずにただ漫然と字を書くことを私は勧める。机に座り、目の前にノートを開き、お気に入りのペン(私は万年筆を勧める)を持ち、気の向くままに字を書く。リラックスしようなどと焦る必要はない。ただ、目的を持たずに字を書くのである。そうすると、自然と心のままに浮かんだ言葉を紙の上に並べることになる。
普段、ぼんやりと感じていることが字になるときもある。何も考えずに、出てきた言葉たちをノートの上に落としていく。そうすると、書かれた文字たちが漠然として曖昧であることに気づく。果たして自分と何の関連性があるのかも分からない。自分自身のあるべき姿からは想像もできない言葉が出てくる。それでも構わない。ただ、その漫然で曖昧な言葉たちをそのまま受け入れるのである。言葉がノートの上で文字として色を持ち、あなたの目の前に浮き出してくる。
その言葉たちは、シンプルで力づよい。自分の心の中を映した言葉だからだ。普段の自分のあるべき姿とは程遠くても、それが自分の言葉なのだ。私たちは普段から、様々な前提を持ち、自分に言い訳をしながら生きている。そして、そのシンプルで力づよい言葉たちは、私たちによって自然と封じ込められてしまっている言葉である。この本質的な問題から目を背けて、私たちは漠然とモヤモヤした気持ちを抱いていたことに気づく。心の奥から染み出した言葉たちは、どんなに不格好で剥き出しであったとしても、自分そのものである。