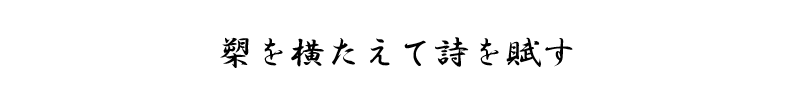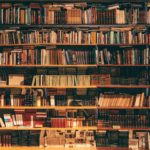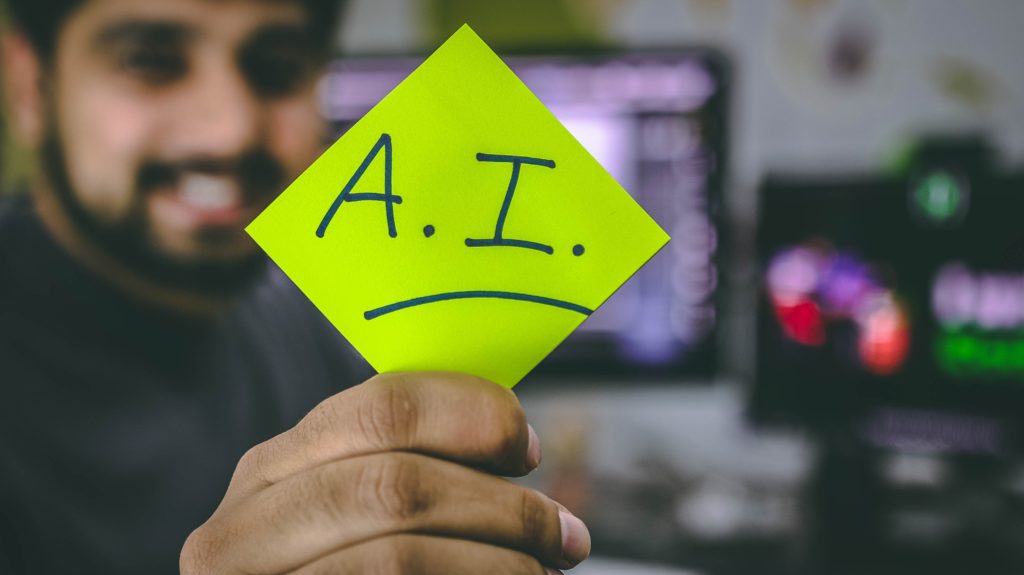
文系AI人材になる 統計・プログラム知識は不要
文系人材がAI時代に何をすべきかが書かれている本。著書は、ZOZOでAIプロジェクトを推進した方。ここでは文系人材と書かれていますが、これはそのまま文系人材をAIコンサルと読み替えてもよいだろう。
この本のエッセンスは、まず、「AIを作る人」と「AIの使い方を考える人」は分かれるという前提を置いている。その上で、理系人材は基本的に「AIを作る人」を目指すため、統計やプログラム知識は必要になる。一方、文系人材は一般的にヒューマンスキルが求められる職種に就くため、おのずと「AIの使い方を考える人」の役割を担うということだ。AIの詳しい構造は理解する必要はなく、どうやれば私たちの生活に役立てるかという視点でAIを捉えることが必要となる。
そして、文系人材はAIに仕事を奪われるどころか、AIと共存する社会を創るために仕事が増えていくといっている。具体的な例として、AIの活用企画であったり、AIを導入するためのマネジメントを文系人材が担っていくことになる。
読んでいて感じたのは、「AIを作る人」というのは、そもそもそんなに職業としてパイが大きくないため、理系人材も「AIの使い方を考える人」になるだろうということ。そもそも、「AIの使い方を考える人」にだってAIに関する知識が相応に求められる。その場合、技術面から理解がしやすいであろう理系人材にも大きな期待が寄せられる。
ただし、冒頭のとおり、人にAIの使い方を伝えたり、人の感情を踏まえてリードしていくことが必要になるから、ヒューマンスキルが重要であることは変わらない。そういう意味では、文系人材という括り方にも違和感はない。どちらかといえば、文系人材というよりAIコンサルに近いイメージだ。
この本の優れた点は、第五章以降の各社の事例だ。食品、金融、医療、教育、公共などの業界の軸で、識別、予測、会話、実行系AIの活用事例が詳しく書かれている。企業でAI活用を検討している人、コンサルやベンダーでAI活用を支援する人には、学びになると思う。
AI経営で会社は甦る
こちらは、コンサルが日本企業に対してAI活用を支援する際に、その勝ち筋が見えてくるようになる本だ。
この本は、著者がいうグローバルからローカルに時代が移ってきているという理論を軸に、情報化の波がカジュアルからシリアスへ(ネットからリアルへ)時代が移ってきている点を踏まえて話が進む。その上で、これからの時代ではローカル経済の不満がもともと少なく、新しいテクノロジに抵抗感が少ない日本には勝機があると説く。
これまではネットでのAI活用が主流であったため、GAFAに圧倒的な差をつけられてしまった日本企業であるが、今後はリアルの世界、つまりは失敗が許されない医療などのシリアスの世界でAI活用が進むことになるため、シリアスなモノづくりに強い日本にはチャンスがあるという。
後半からはプロ経営者理論や、著者の独自哲学が入ってくるため、前半が重要だ。単純に日本がAI時代で勝機ありということに元気づけられる本だと思う。
まるわかり!人工知能 ビジネス戦略
こちらは、日本企業でのAI活用の具体例が良く分かる本。
食べ物の不良検知、タクシーの需要予測、養殖のIoTなどなど…、日本企業のAI活用事例が数十事例ほど詳細に書かれている。AIの導入失敗事例についても生々しく書かれており、そこが最も参考になるところではないだろうか。